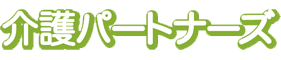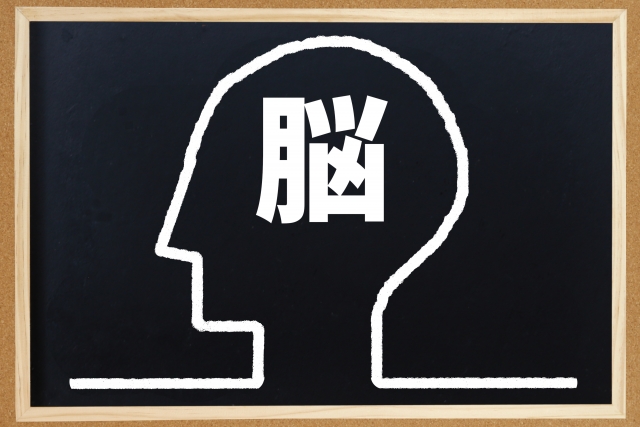介護現場で行う利用者の「脳トレ」には、実は様々な意味や効果が期待されます。
実際に多くの介護施設やデイサービスなどでも実施されている脳トレですが、どのようなことが期待できるのか紹介します。
脳トレは認知症予防につながる
年齢を重ねれば脳内の血流も悪くなるため、エネルギーを脳へと運ぶ酸素や糖分が不足がちになり認知機能に影響を及ぼします。
認知機能が衰えれば「認知症」になる可能性もあるため、「脳トレ」により脳を刺激し、脳内の血流促進や認知機能低下予防につなげましょう。
人の脳は、
- 前頭葉
- 側頭葉
- 頭頂葉
- 後頭葉
の4つに区分されており、前頭葉の前頭前野が記憶・学習・感情などを調整する役割を担います。
前頭前野を活性化させれば脳の老化を遅らせることができますが、そのためにも脳トレを続けることが大切です。
脳トレは介護施設やデイサービスでもすでに実施されている
脳トレは認知症予防や症状を鈍化させる効果が期待できますが、すでにいろいろな介護施設やデイサービスでも実施されています。
高齢の方が楽しむことのできるレクリエーションの一環として取り入れられることが多く、
クイズやゲームなどの脳トレを活用するケースが一般的です。
飽きることなく続けることができるように、使いやすいものや好まれやすいものを選ぶとよいでしょう。
脳トレを使ったレクリエーションを行うとき注意したいこと
脳トレは、「正解」を出すことを目的としていない点には注意してください。
利用者が間違えたりミスをしたりしてもそれ自体は問題ではなく、楽しみながら脳を鍛えることができればよいと考えましょう。
間違いやミスを指摘したり非難したり、自信を失う言葉や態度を見せれば参加することを拒むようになる可能性もあります。
ポイントは誰でも簡単にできるものを続けること
介護施設で行う脳トレでは、なぞなぞやしりとりなど誰でも簡単にできるもののほうが安心です。
簡単なものなら継続しやすく、誰でも参加できるからといえますが、飽きることがないように幅広い分野のゲームを取り入れる工夫もしましょう。
頭で考え問題を解くだけの脳トレよりも、発声したり体を動かしたりなど、より多くの部分に刺激を与えるゲームなどであれば楽しさも感じられます。
また、単独で行うトレーニング以外にも、2人1組やチームになって行うことのできる内容も取り入れるとよりよいでしょう。
それによりコミュニケーションを生むことができ、脳に対する刺激はより強まるはずです。

介護現場におすすめの脳トレ
介護現場でおすすめの脳トレは、誰でも簡単に参加でき楽しんでできるものです。
クイズやなぞなぞ、しりとりなどであれば誰でも参加できますが、いつも同じ内容では利用者もあきてしまいます。
そこで、簡単にできるもののいつもとは少し違うおすすめの脳トレをいくつか紹介します。
回文
文字列が上から読んでも下から読んでも同じ言葉になる文句を「回文」といいます。
たとえば、
- やおや(八百屋)
- しんぶんし(新聞紙)
などの言葉や、
- たけやぶやけた(竹藪焼けた)
などの早口言葉に使われる言葉です。
簡単な例文を示しルールを説明した後に、自由に利用者に考えてもらいましょう。
頭の体操になるだけでなく、数字列を反対に読むことと同様に、認知機能維持によい効果をもたらすことが期待できます。
利用者が考えた回文は、実際に声に出して読み上げてもらうことで、脳トレの効果がより高まるでしょう。
点つなぎ
数字やアルファベットなどを書いた点を順番に線で繋ぐ遊びを「点つなぎ」といいます。
点を繋ぐと最後に一筆書きの絵が完成することが特徴で、完成する絵柄はシンプルな図形の場合もあれば、複雑な形や動物・風景などいろいろです。
単純な遊びと感じるかもしれませんが、数字やアルファベットなどを順番に探しながら追いかけ、線を繋ぐ動作は脳だけでなく手を使う運動にもなります。
脳に対する刺激で自律神経のバランスも整えることができ、何が完成するのかワクワクしたり想像したりするため、イメージ力も向上させることができます。
誰かと点数を競う脳トレではないため、勝ち負けを気にせずストレスも感じず、リラックスした雰囲気で楽しく行えることがメリットです。
指先体操
指先を動かす体操を「指先体操」といいます。
「第2の脳」といわれる指先は、脳につながる神経が多く存在しているため、動かすことで脳へと刺激が伝わり脳活動を活発化させます。
指先だけを体操に使うため、特に大がかりな準備も必要ありません。
様々な方法がありますが、たとえば両手の指を曲げ伸ばしする体操や、手を広げた状態から親指・人差し指・中指…と順番に折り曲げていき、グーの状態から今度は反対に小指から伸ばす「指先マラソン」もあります。
普段と異なる指の動きをすることで、脳によい刺激を与え活性化させることが期待できます。